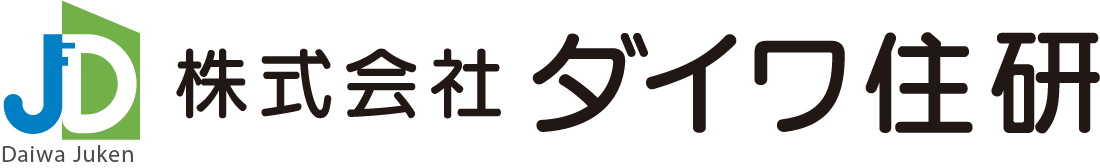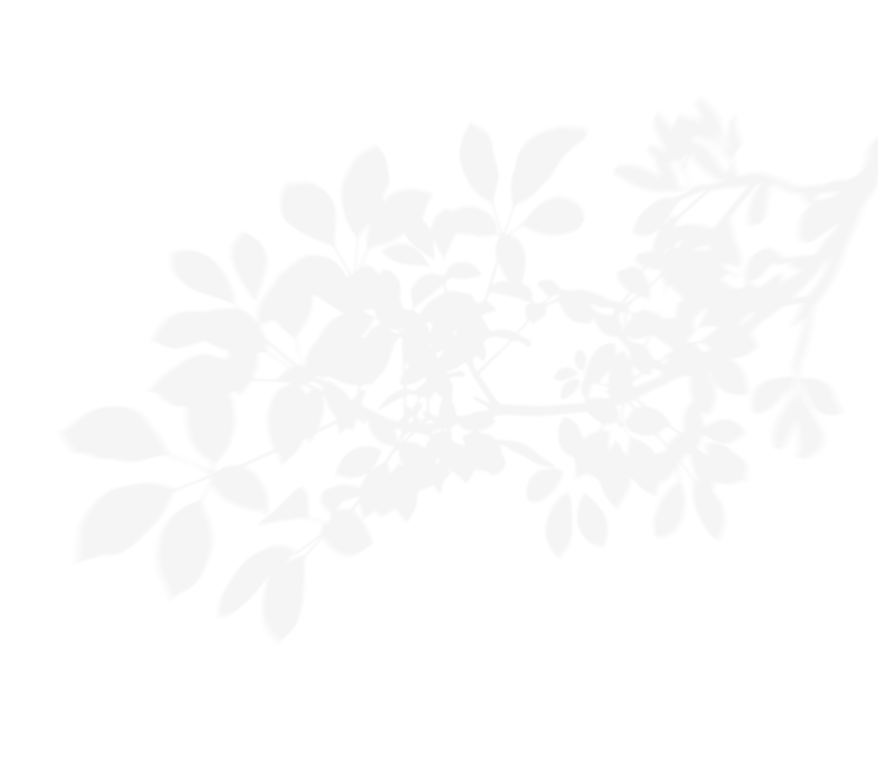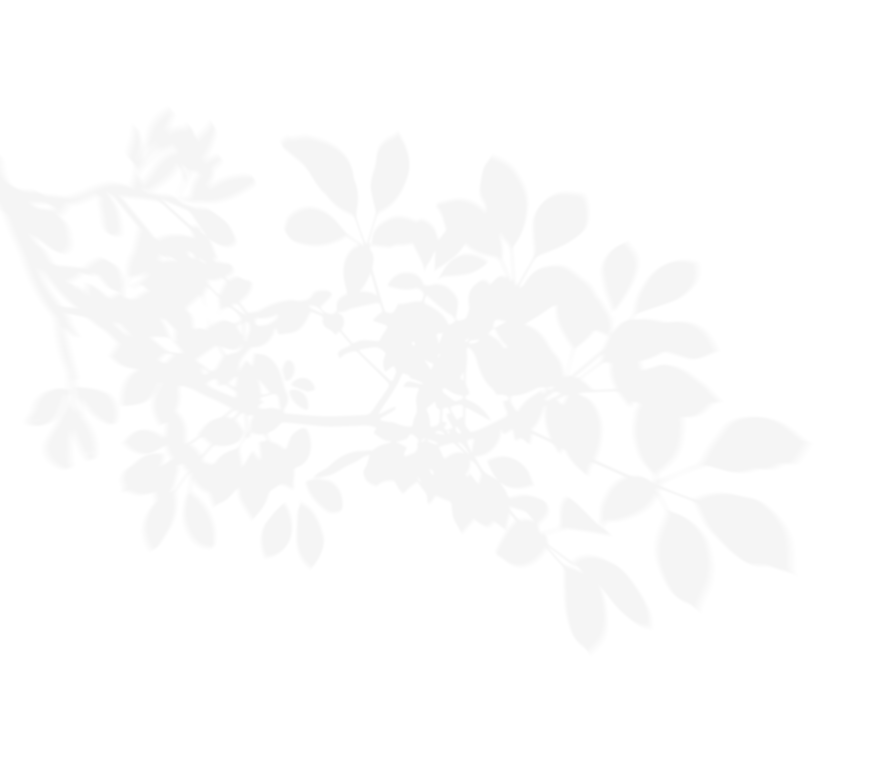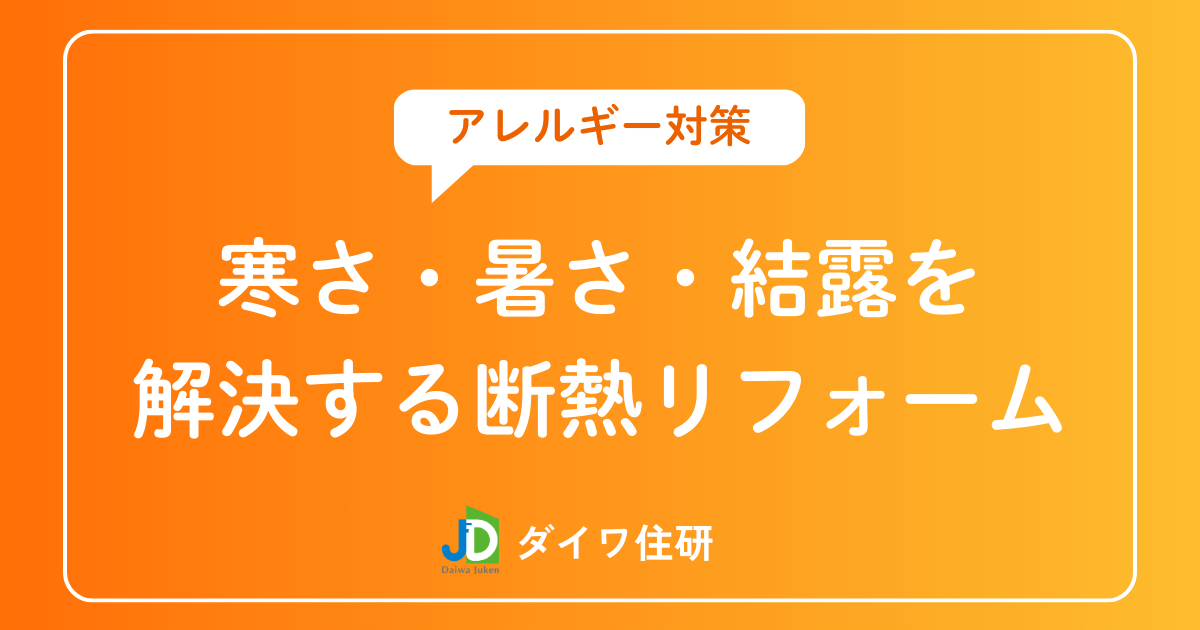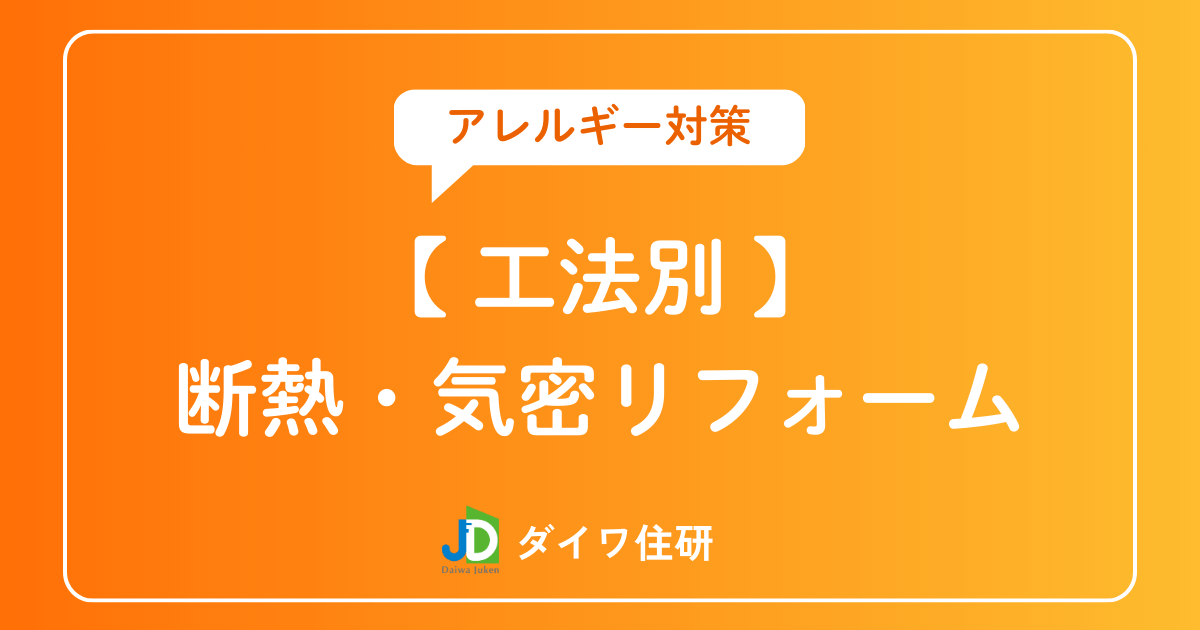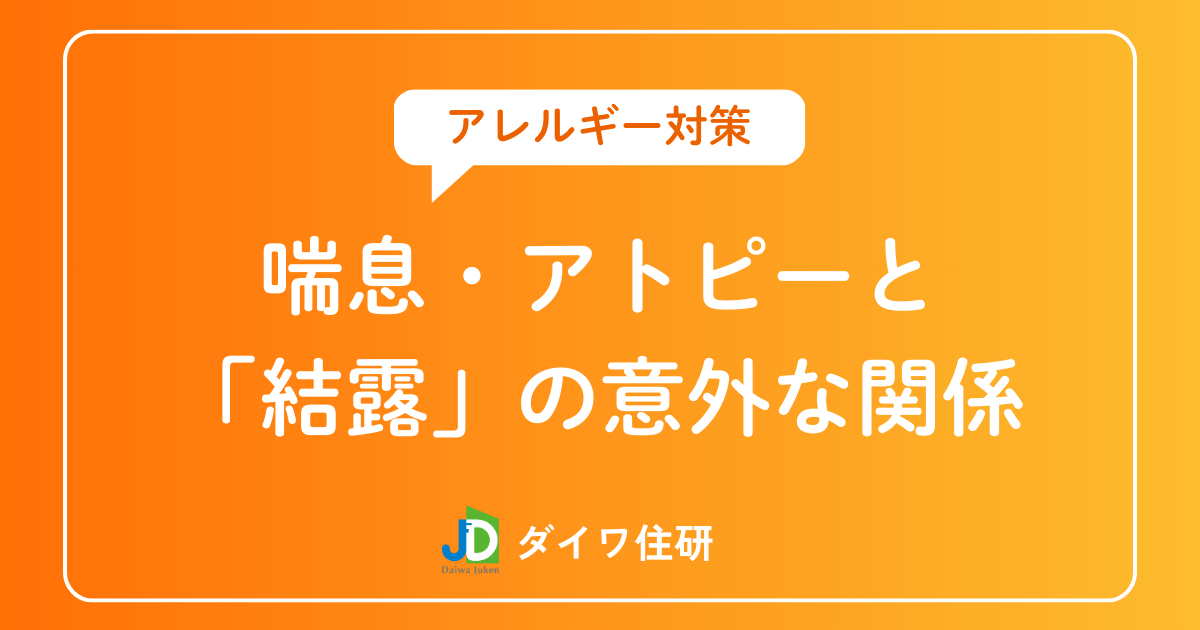通院しても治らない家族の【喘息】、原因は「家の構造」かもしれません。
2025.8.6
アレルギー対策
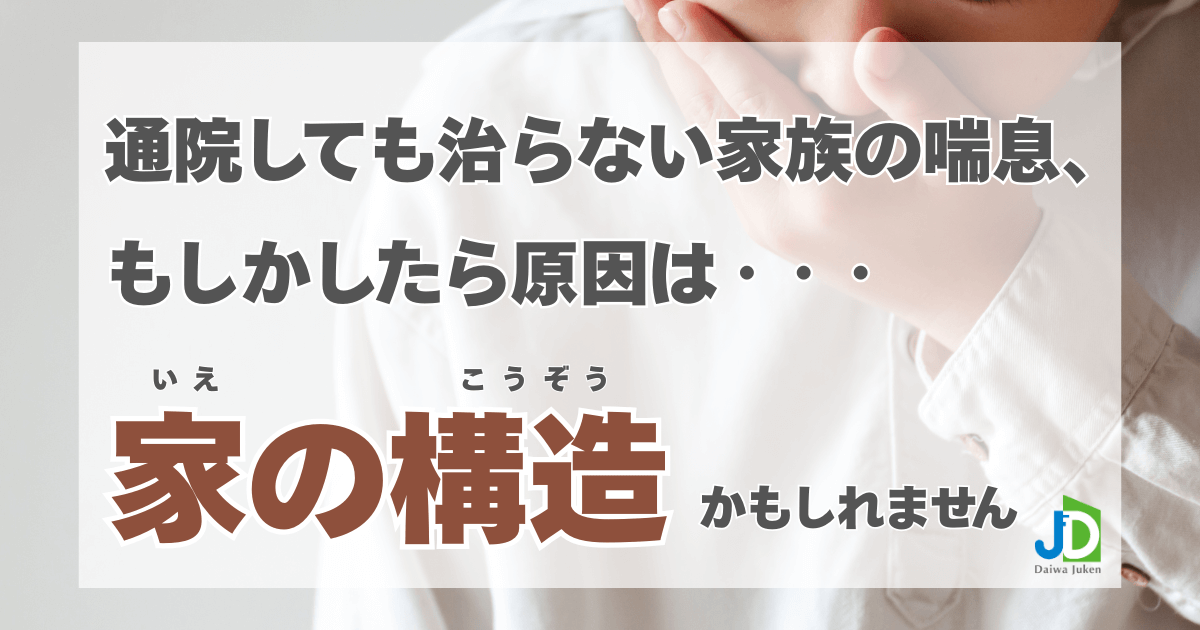
毎日続くご家族の咳や、皮膚のかゆみ。何度も病院に通い、掃除や空気清浄機で対策しても、なかなか症状が改善しない。あなたは今、「もう何をしたら良いのだろう」と、深い無力感を感じているかもしれません。
その悩みの根源は、薬や日々の対策では解決できない「家の空気」にある可能性が非常に高いです。
【家の空気は、家族の健康を守る最後の砦です。】その「見えない空気の質」が、カビ、ダニ、化学物質といったアレルゲンを運び、知らず知らずのうちにご家族の健康を蝕んでいるのです。
この記事は、アレルギーのプロである工務店が、ご家族の喘息やアレルギーの原因となる問題を科学的に解明し、掃除や薬では届かない家の構造から考える根本的な解決策を提示します。
いきなり対策に進む前に、ひとつだけ整理してください
症状がつらいと、
「早く何とかしたい」
「原因を特定したい」
と、どうしても気持ちが先に進みます。
ただ、ここで多いのが
原因が整理できないまま、対策や工事の話に進んでしまうことです。
アレルギーやシックハウスの不安は、
医療・体質・住まいの条件が重なって起きるため、
順番を間違えると、遠回りになります。
▶ アレルギー?シックハウス?──工事の前に「住まい側で確認・整理できること」があります
このページでは、「どこから疑うべきか」「何を先に確認すべきか」を、住まい側の視点で整理できます。
【この記事で分かること】
●家族のアレルギーや喘息の原因が、掃除や薬では解決できない「家の空気と構造」にあること。
●浴室・寝室・収納など、家の中の場所別に今日からできる即効性の高いカビ・ダニ・結露対策。
●結露・湿気・カビ・ダニといったアレルゲンが家の中で発生する科学的な仕組みと危険な箇所。
●断熱・気密・換気・防露など、家の構造から根本的にアレルギーを改善する長期的な解決策。
●「空気清浄機や掃除の限界」を知り、最終的に家族の健康を守るための具体的な行動。
なぜ「家」がアレルギーの温床になるのか
室内空気は「見えない食べ物」
ご家族のために、安全な食材を選び、栄養バランスの取れた食事を作っていることでしょう。しかし、食べ物以上に、私たち家族が生命を維持するために、無意識のうちに大量に取り込んでいるものがあります。それが「空気」です。
【知らないうちに、子どもは“家の空気”を食べています】
私たちは、一日に食べ物(約1.3kg)や飲み物(約1.2kg)と比較して圧倒的に多い、およそ13kgもの空気を呼吸によって体内に取り込んでいます。
空気は、まさに「見えない食べ物」であり、その質がご家族の健康をダイレクトに左右します。
家に潜むアレルゲンの発生要因
喘息やアレルギーを引き起こす原因は、カビやダニだけではありません。建材や家具から放出される化学物質も、ご家族の健康を脅かす重大な問題です。これらの問題はまとめて「シックハウス症候群」とも呼ばれ、すべて「空気の質の悪さ」という一つの根っこから発生しています。
弊社のシックハウス対策について詳しくはこちらをご覧ください。
その最大の理由は、アレルゲンがあなたの掃除の手が届かない場所で、構造的に発生しているからです。カビやダニといったアレルゲンの発生は、以下の4つの要因が複雑に絡み合って起こる「家の仕組み」なのです。
【アレルゲン発生の悪循環フロー】
1.高湿度の停滞と換気不足
↓
2.逃げ場のない「結露」
↓
3.【壁の中の結露】がカビを呼ぶ:【実は“壁の中”でも結露は起こっています。】
↓
4.アレルゲンの爆発的増加
下記の写真をご覧ください。壁を外してクロスをめくってみると・・・

【地域特性コラム】滋賀県の結露リスク:琵琶湖と流れ込む河川
滋賀県は、この「結露」と「高湿度」の問題を抱える地域です。
・琵琶湖と河川による年間を通じた高湿度
琵琶湖や河川の水面から蒸発する大量の水蒸気によって、滋賀県は周囲の地域に比べて年間を通して湿度が高くなります。これは、結露を引き起こす根本的な原因です。
・夏型結露の脅威
最近の酷暑により夏場の冷房は、使用が不可欠になっています。冷房で室内を冷やしすぎると、琵琶湖や河川からの高湿度な空気が壁内や床下で冷たい配管などに触れ、見えないところで結露する「夏型結露」のリスクが高まります。これが、構造材の腐食やカビ・ダニ繁殖を助長する、滋賀県特有の大きな課題です。

今日からできる即効アレルギー対策
【すぐできる小さな工夫が、家族を守ります。】
浴室・脱衣所:湿気の滞留を防ぐ
今すぐ実践!浴室・脱衣所の湿気ブロック作戦3原則
▶原則1:換気扇は「つけっぱなし」が正解
カビは湿度70%以上で活発に繁殖します。換気扇を24時間稼働させることで、常に湿気を屋外に排出し続け、カビの好む高湿度な環境を断ちます。
▶原則2:入浴後の「ひと拭き」をルーティンに
カビの成長には水分が不可欠です。水滴を拭き取ることで、カビの生命線である水分を物理的に取り除き、栄養源となる石鹸カスや皮脂を洗い流す効果もあります。
▶原則3:脱衣所の湿度に気を配る
洗濯物の部屋干しは、脱衣所の湿度を80%以上に押し上げ、家全体に湿気を拡散させる原因になります。除湿機や窓の開放で湿度を60%以下に抑えましょう。
収納スペース:カビ臭の根は“空気の滞留”
床に物を置かないようにしてください。置く物をが増えるとその上にホコリが積もってしまいますので、物は収納スペースに置いて、床のお掃除はサッと簡単に済ませられるようにしておくことがポイントです。
収納スペースの湿気とカビを防ぐ3つの鉄則
▶鉄則1:壁から離し、奥に「空気の通り道」を作る
荷物を壁に密着させると、冷たい外壁に接する壁の表面温度が下がり、空気の対流がないため結露が発生しやすくなります。隙間を作ることで空気の動きを促し、結露を防ぎます。
▶鉄則2:「扉を開ける換気」を定期的に
クローゼットや押入れは空気が滞留しやすく、湿気が閉じ込められがちです。定期的に扉を開けて強制的に空気を入れ替えることで、カビの胞子や湿気を排出し、アレルゲン濃度を下げます。
▶鉄則3:詰め込みすぎず、「7割収納」を意識
空間に余裕を持たせることで、空気の層が生まれ、収納内部の湿度を均一に保ちやすくなります。これにより、衣類などに湿気が閉じ込められ、局所的なカビが発生するのを防ぎます。

寝室:ダニ対策の最重要エリア
寝室の空気とダニを断つ3つの習慣
▶習慣1:布団は起きたらすぐに「湿気を逃がす」
人は寝ている間にコップ約1杯分(約200ml)の汗をかき、布団やマットレスに吸収されます。この湿気はダニが好む環境(湿度70%以上)を作るため、すぐに畳まず湿気を逃がすことで、ダニの繁殖スピードを鈍化させます。
▶習慣2:掃除機は「かける回数」より「かけ方」
ダニの死骸やフン(アレルゲン)は非常に軽く、また繊維の奥に潜んでいます。ゆっくり時間をかけて吸引することで、アレルゲンの舞い上がりを防ぎつつ、繊維の奥のダニを効率的に除去できます。
▶習慣3:高密度カバーと「熱処理」
ダニは熱に弱く、50℃以上の環境で死滅します。布団乾燥機や高温洗濯による熱処理は、ダニを殺す最も確実な方法です。高密度カバーは、既にいるダニのアレルゲンが外に出るのを防ぐ効果もあります。
リビング:埃=アレルゲンの運び屋
リビングから埃とアレルゲンを減らす3つのコツ
▶コツ1:掃除は「上から下へ」が鉄則
埃は空気中を舞うため、高い場所から先に掃除をすることで、下に落ちた埃を最後にまとめて掃除機で除去でき、二度手間を防ぎます。
▶コツ2:床材を「埃を閉じ込めるもの」から変える
カーペットやラグは埃を大量に吸着し、ダニの温床になりやすいです。フローリングなど拭き掃除が可能な床材に変えることで、アレルゲンの除去が格段に容易になります。
▶コツ3:エアコン内部を定期的にチェック
エアコン内部は高湿度のカビの温床になりやすく、運転時にカビの胞子を部屋中にまき散らします。専門業者によるクリーニングは、アレルゲンを物理的に取り除く最も確実な方法です。
窓・結露対策
結露を抑えカビを防ぐ3つの応急処置
▶処置1:発生したら「こまめに拭き取る」
結露水は、カビが発芽・成長するための水分供給源です。水分がある状態を放置すると、窓枠やパッキンに黒カビが根を張ってしまうため、水滴を拭き取ることでカビの生命線(水分)を断ちます。
▶処置2:窓際と部屋の温度差を小さくする
結露は、室温と窓表面温度の差(露点温度)が原因です。厚手のカーテンなどで窓を覆うことで、窓の表面温度が外気に冷やされるのを防ぎ、結露の発生しきい値を超えないように調整します。
▶処置3:常に「換気」を行う
新鮮な空気を継続的に取り入れることで、湿気の滞留を防ぎ、湿気をためないことでカビやダニの繁殖リスクも大幅に減らせます。家庭内では人の呼吸・料理・洗濯・加湿など、一日中水蒸気が発生しており、短時間の換気だけでは十分に排出しきれません。
アレルゲン別・要点まとめ
カビ・ダニ・花粉・ペットの違い
| アレルゲン | 主な症状 | 発生しやすい場所(家の中の敵) | 対策のポイント |
| カビ | 喘息、アトピー、アレルギー性鼻炎 | 浴室、収納の奥、窓枠、エアコン内部、壁の裏側 | 湿度を50%以下に抑え、水分(結露水)を断つ。 |
| ダニ | 喘息(特に夜間・早朝)、アトピー | 寝具(布団・マットレス)、布製ソファ、カーペット | エサ(フケ・アカ)と湿気(60%以上)を断つ。 |
| 花粉 | 鼻炎、結膜炎、咳 | 窓際、洗濯物、玄関 | 外気の侵入を最小限に抑える。 |
| ペット | 鼻炎、皮膚炎 | ペットの寝床、毛が溜まりやすい場所 | 換気と物理的な除去(掃除)を徹底する。 |
家のアレルゲン危険箇所チェック
代表的な危険箇所5選
| 危険箇所 | なぜ危険か | チェックポイント |
| 1. 外壁に面した北側の押入れ | 外気に冷やされ結露が起こりやすい。空気が滞留し、カビの温床になりやすい。 | 奥の壁、床、収納している衣類にカビ臭がないか、湿っぽくないか。 |
| 2. 洗濯機パンと壁の間 | 湿気の多い脱衣所の中でも、最も埃と湿気が溜まりやすく、カビが増殖する。 | 洗濯機を動かして、奥の壁や床に黒カビが生えていないか。 |
| 3. 窓とカーテンの隙間 | 結露水がカーテンを湿らせ、カビが繁殖。窓を開けるたびに胞子が室内に舞い込む。 | カーテンの裾や窓枠の下側に、黒ずみやカビ汚れがないか。 |
| 4. 玄関と下駄箱 | 外から入る花粉や土埃、靴から出る湿気がこもり、カビと花粉の混ざった埃が充満。 | 下駄箱の奥や靴の裏にカビが生えていないか。 |
| 5. 床下換気口の周辺(古い家) | 床下からの湿気が壁の隙間を伝って室内に流れ込み、見えない壁の中で結露・カビ発生の原因になる。 | 床が冷たく、壁のコンセント周りなどが変色していないか。 |
家の構造から考える根本改善
【地域特性コラム】滋賀県の結露リスク:琵琶湖と流れ込む河川で確認した通り、琵琶湖の影響で年間を通して湿度が高く、夏型結露まで起こる滋賀県の気候では、日々の努力だけでは限界があります。ご家族の健康を守るためには、アレルゲンを寄せ付けない【高気密・高断熱住宅】に変えることが不可欠です。
高気密・高断熱住宅とは、家の隙間をなくして熱を逃がしにくくし(高気密)、断熱材で熱を伝えにくくする(高断熱)ことで、外気温の影響を受けにくい快適な室内環境を保つ家のことです。冷暖房の効率が良くなり、省エネルギーで光熱費も抑えられ、低アレルギーの家には欠かせない環境づくりです。詳しく説明していますのでぜひご覧ください。
断熱(アレルゲンの土壌を断つ)
高断熱化は、家のアレルゲン対策の土台です。断熱性能を高めることで、壁や窓の表面温度が外気に左右されにくくなり、室内外の温度差を小さく保ちます。これにより、カビやダニの最大の発生源である「結露」そのものを防ぐことが可能です。温度ムラのない家は、冷たい部分がなくなり、アレルゲンが繁殖しにくいクリーンな環境を実現します。
気密(悪い空気の侵入を防ぐ)
どんなに高性能な換気システムも、気密性が低いと効果を発揮できません。家全体の隙間をなくし高気密にすることで、花粉やPM2.5、未処理の湿気を含んだ外の空気が、壁の隙間などから勝手に侵入するのを防ぎます。これにより、空気の流入口と排出口がコントロールされ、高性能フィルターを通した清浄な空気だけを計画的に取り込むことが可能になります。
換気(清浄な空気だけを取り込む)
滋賀県のように高湿度の地域では、ただ窓を開けるだけの換気では不十分です。高気密・高断熱住宅では、熱交換型換気システムが必須となります。これは、室内のカビが好む高湿度の空気を排出しつつ、花粉やPM2.5などのアレルゲンをカットした新鮮な空気だけを取り込む仕組みです。常にクリーンな空気を循環させ、家中の湿気を効率的にコントロールします。
防露(壁の内部を守る)
壁の内部で結露が発生し、構造材を腐食させる「壁内結露(壁体内結露)」を防ぐため、水蒸気の透過を防ぐ防湿層を適切に施工します。特に夏型結露のリスクが高い滋賀県において、この防露設計は住宅の長寿命化と健康維持に欠かせない技術です。
実は、目に見えるカビよりも、目に見えないところの壁の中や、床下、天井にカビが生えていることがあります。あわせて、壁の中の結露について説明していますのでご覧ください。
いきなり工事の話に進む前に、
「住まい側で何を確認・整理すればいいか」を一度まとめておくと、判断を間違えにくくなります。
「アレルギー?シックハウス?──工事の前に住まい側で確認・整理できること」
よくある質問(FAQ)
掃除だけでアレルギーは改善しますか?
A. 根本的な解決にはつながりません。
掃除は、床や家具表面の「アレルゲンを除去する」行為であり、カビやダニの「発生源を断つ」ことではありません。特に家の構造的な欠陥(壁内結露や床下からの湿気)が原因の場合、アレルゲンは無限に発生し続けます。家の湿度環境が変わらない限り、掃除をしても数時間後にはアレルゲン濃度が元のレベルに戻ることが専門家の研究でも示されています。
空気清浄機で十分ですか?
A. 発生源対策にはなりません。
空気清浄機が除去できるのは「空気中を浮遊しているアレルゲン」に限られます。しかし、アレルギーの原因となるダニのフンや死骸の多くは寝具やカーペットの繊維の奥に潜んでおり、カビの胞子は壁の裏や床下に付着しています。空気清浄機は「湿気」の発生源を断つことはできず、カビ・ダニの繁殖環境そのものを変えることはできません。家全体の湿度を計画的にコントロールできる高性能な換気システムとは、役割が根本的に異なります。
リフォームで改善できますか?
A. はい、適切におこなえば有効な改善策になります。
特に「窓(断熱サッシへの交換)」や「壁(断熱材の補填)」の改修は、表面結露や壁内結露を大幅に防ぎ、カビ・ダニの繁殖環境を根本から奪います。さらに、熱交換型換気システムを導入することで、高性能フィルターによる外部アレルゲン(花粉など)の侵入を防ぎながら、家全体の湿度をコントロールする高気密・高断熱住宅に近い環境を実現できます。
まとめ:空気が変われば家族が変わる
通院しても、薬を使っても改善しなかったご家族の喘息やアレルギー。その原因は、家が持つ「構造的な湿気と空気の質の問題」にあったかもしれません。
【空気が変わると、家族の未来が変わります。】
私たちは、カビやダニが発生しにくい湿度コントロール、花粉をカットした清浄な空気、そして一年中快適な温度環境を実現する家の専門家です。
ご家族が心から安心して過ごせる、清々しい空気の家づくりのご相談を心よりお待ちしております。
「一度、家の状態を見てほしい」とお問合せいただければ、まずはお家の原因を調査いたします。
【無料相談】【無料の簡易診断】アレルギー、喘息対策に強い家づくり
執筆者プロフィール

和田 隆之(わだたかゆき)
株式会社ダイワ住研 代表取締役
45年にわたり約3,800件の工事を手がける。25年前、自宅を建て替えた際に娘がぜんそくを発症。
この経験から、断熱性ばかりを追求した家が必ずしも健康的ではないと気づき、現在は、家族が健康に暮らせる「空気のきれいな家」の重要性を伝え、住環境の改善に尽力している。